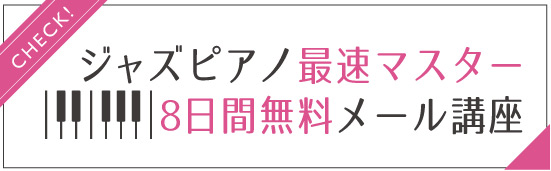なぜジャズピアノはアドリブするのが難しいのか

もくじ
最もアドリブしやすいのは歌
最近は、メルマガ読者さん向けに
ZOOMグループレッスンを
期間限定でやっています。
(~ 2020.5.31迄)
1時間の中で、
一つテーマを決めての
レッスンをしていますが、
先日スウイング攻略を
扱いました。
今回は、
スウィングについての内容を
お話します。
日本人は元々、
スウィングが苦手だというのは、
ご存知でしょうか?
なぜなら、前のめりの
音頭系民族だからです。
一方で欧米人は、
生まれた時からアフタービートで
育っていますので、
この時点で日本人は不利です。
しかも、
ピアノは楽器の特性上、
更にスウィングが不利です。
なぜなら、
アドリブをイメージする
脳と楽器の距離が遠いからです。
脳と楽器の距離が最も近いのが、
歌で、
その次に近いのが、
吹奏楽器です。
動画でも説明しています。
なぜピアノはノリよくアドリブするのが難しいのか
5分15秒
アドリブはイメージが先行しないと弾けない
脳と楽器の距離が、
遠い、近いというのは
どういうことか説明します。
アドリブは、
脳のイメージが先行して
初めて出来るものです。
つまり、
イメージ出来ないものは、
アドリブが出来ません。
更に、
スウィングのノリが
体に入っている状態が、
アドリブに反映されます。
ボーカリストは、
自分の体が楽器なので、
脳のイメージがダイレクトに
表現出来ます。
また、
吹奏楽器は、
自分の口の延長に楽器があり、
息を吹き込むため、
脳と楽器の距離感が近く、
イメージがアドリブに
直結しやすいです。
一方でピアノの場合、
直接声を出すわけでもなく、
息を入れるわけでもありません。
楽器を弾くのが、
機械操作のような
ところがあります。
そのため、
脳のイメージと
楽器に距離感があります。
距離が遠くなるほど、
イメージをダイレクトに
アドリブに反映させるのが
難しくなります。
分かりやすく言うと、
ダンスは体を使うため、
ダイレクトなアドリブですよね。
このように、
ピアノでアドリブをするのは、
他の楽器に比べると
難しいところがあるのです。
こういった点から、
ピアノは感覚だけで弾くことは難しく、
他の楽器よりも知識で処理することが多く、
ロジカル、幾何学的なアドリブを
得意とする楽器です。
弾く前に歌ってイメージを作る
ここで、
アドリブが慣れていない方に
オススメな練習方法があります。
それは、
楽器を演奏する前に、
口で歌うことです。
アドリブが初心者の方に、
馴染みあるテーマを歌ってもらったり、
2音程度の簡単なフレーズで
鼻歌のようなメロディを
歌ってもらうと、
すんなり歌えます。
これを何度か繰り返すことで、
脳がアドリブのイメージを
掴みます。
ここで初めて、
楽器を使うとアドリブへの
抵抗が減り、
自然なフレーズが演奏出来ます。
ただし、
あまり複雑なメロディにせず、
2音程度でノリ良く
弾くことこを大事にしましょう。
細かい音やスケールの話は、
そのあとで大丈夫です。
是非、試してみて下さいね。
理論的な知識も更に知りたい方は、
こちらにまとめています。
宜しければご覧になって下さいね。
https://keiko-onuki.com/jazzpiano/

アドリブ初心者の為の
体系的に学べるレッスン
ジャズピアノ&アドリブコーチ
性格気質と自己表現の研究家
音大&ジャズ研未経験で、ピアノブランク13年、30歳でコードを知る。
約8年間ジャズピアノの実態が分からなかったが、ある時ヒラメキが起こり、何を何からやったら、誰でもジャズピアノが弾けるのかが分かり、1日6時間くらいピアノに夢中になる。
2016年より1児の母をしながらリアル&オンラインコーチングレッスンを開始し、ゼロベースの初心者でも、1年以内にリードシートのみで、アドリブ、セッションに参加できる体系的なメソッドを提供中。
更に、なぜ自分はアドリブが弾けるようになったのかが、心理学や脳科学の観点で説明が出来ることが分かり、楽器・アドリブの熟達法と内面性の関係について、レッスン、YouTube、ブロブ、メルマガで語っている。