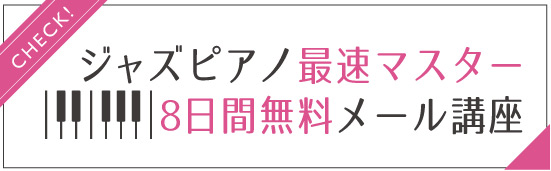リディアン7を使ってジャズピアノの知識を感覚に移行する方法

もくじ
知識だけでも感覚だけでもアドリブは出来ない
今までみなさんはどんなレッスンや
どんな練習をされてきたでしょうか?
ジャズピアノは、他の楽器と違って正直、
覚えることは多いです。
私自身、覚えることはとっても苦手なので、
今行っているレッスンでは、
覚えることを最小限にとどめたものを
体系化しました。
ただ、何かを削ったのではなく、
突き詰めていくと、シンプルだと分かったので、
覚えることが最小限になったような感じ、
と言うものです。
そして、覚えることは覚えた後、
とっても大事な事があります。
それは、覚えた段階では知識のままなので、
更に覚えたものを感覚に落とし込む作業が
必要だということです。
知識を感覚に移行するという作業が
抜けているがために、
スケールやヴォイシングはある程度弾けるけど、
曲では歌える感じがしない、
面白くない、と言われる方が多いです。
また、
極端に、先生の趣味に付き合わされた、
ロジカルなレッスンばかり受けた方、
極端に、とにかく曲を聞きなさいと
ざっくりした感覚的なレッスンばかり受けた方。
このような方たちが、私のところに来て、
アドリブが出来ないと相談されます。
同じスケールでも感覚が違うことに気付けるか
今日は、一つ例をあげます。
リディアン7というスケールをご存知でしょうか?
このスケールを知らない方は、
ご自身で調べてみて下さいね。
曲中にⅡ7若しくは、Ⅶ♭7が出てくると、
どちらのコードにも、
このリディアン7というスケールを使います。
だから、多くの人は、
同じスケールを使えばいいんだね!
となります。
でもですね、この説明の段階では、
実は知識レベルでは知っているというものです。
これだけだと、曲で歌える感じがしませんよ。
実際弾いてみると分かりますが、
Ⅱ7の時のリディアン7と、
Ⅶ♭7の時のリディアン7では、
全く感覚が違います。
ここが、知識を感覚に移行する作業です。
弾くと分かりますが、同じスケールなのに、
Ⅱ7とⅦ♭7の役割が違うので、
同じ種類のスケールなのに、
雰囲気や音の聴こえ方、
スケールのキャラクターが全く違うように聞えます。
ここまで感覚的にとらえ、
更になぜ違って聞こえるのか?を
口で説明できるかどうかが、
本当に分かって弾けるレベルです。
ですから、
音楽は知識だけでは弾けませんし、
感覚だけでも行き詰まります。
入り口はロジカルな知識でも、
実践主義の感覚でも構いませんが、
自分で弾いていて納得いかないという
違和感があるなら、
知識か感覚かに偏っている可能性があります。
その時は、
知識と感覚を繋げる作業をすると、
いろいろなことが腑に落ちて
確信を持って気持ちよく
演奏が出来るようになりますよ。
知識と感覚をバランスよくまとめた
ジャズピアノの全体像はこちらです。
宜しければご覧になって下さいね。
https://keiko-onuki.com/jazzpiano/

アドリブ初心者の為の
体系的に学べるレッスン
ジャズピアノ&アドリブコーチ
性格気質と自己表現の研究家
音大&ジャズ研未経験で、ピアノブランク13年、30歳でコードを知る。
約8年間ジャズピアノの実態が分からなかったが、ある時ヒラメキが起こり、何を何からやったら、誰でもジャズピアノが弾けるのかが分かり、1日6時間くらいピアノに夢中になる。
2016年より1児の母をしながらリアル&オンラインコーチングレッスンを開始し、ゼロベースの初心者でも、1年以内にリードシートのみで、アドリブ、セッションに参加できる体系的なメソッドを提供中。
更に、なぜ自分はアドリブが弾けるようになったのかが、心理学や脳科学の観点で説明が出来ることが分かり、楽器・アドリブの熟達法と内面性の関係について、レッスン、YouTube、ブロブ、メルマガで語っている。