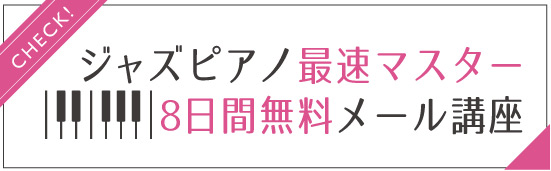ジャズピアノ初心者がフレーズコピーをしない方がよい理由

もくじ
あなたはなぜフレーズコピーをしたがるのですか?
今日は、
初心者が誰かのフレーズコピーを
しない方がよい理由について
お伝えします。
あなたは、
ジャズピアノでアドリブ上達の目的で、
今まで誰かのアドリブコピーをしたことが
ありますか?
私は、何度かあります。
当時の私は、
どんなふうにアドリブのマスターを
していいのか分からず、
とりあえず、
コピーをしてみようと思って
やっていました。
ですが、
コピーも大変で、何時間かけても
数小節くらいしか聞き取ることが出来ず、
結局、コピーは断念しました。
今では、
耳コピアプリのようなものがありますので、
決して難しくはないようですが。
きっとみなさんも、
同じような経験をされたことが
あるのではないでしょうか。
まず、
最初に耳コピをする人の
本当の目的ってご存知でしょうか?
私がいろいろな方の話を聞く限り
知るものをあげてみます。
1、自分のアドリブがダサいから、誰かのカッコイイフレーズを弾く
2、アドリブマスターといえばコピーだよと、教えられたから
3、そのアーティストが好きだから研究している
大きくこの3つです。
問題なのは、上記2つです。
もし、あなたが上記2つに該当するならば、
その作業は考え直した方がいいです。
なぜコピーがダメなのか
では、
なぜコピーを勧めないのかについてです。
それは、
アドリブが殆ど出来ない人にとって、
コピーがアドリブマスターの手段には
ならないからです!
コピーが威力を発揮するのは、
ある程度アドリブが出来る方です。
アドリブが出来るようになるには、
1つ1つの音のキャラクターを
知識と耳の感覚で認識する必要があります。
もし、
誰かのフレーズをコピーしたり、
書いてあるフレーズを弾くだけだと、
1音1音の音のキャラクターの違いが
分からない状態がずっと続いてしまいます。
どういうことかというと、
沢山の音を使われたフレーズの内容に
こだわるほど、
視覚情報でフレーズをキャッチするため、
音を聴覚レベルで認識する力が
つかないのです。
アドリブが出来ない初心者の人は、
まずは、
1音1音を鳴らして、
その音が相対的にどんな音に聴こえるか、
これを知識と合わせながら、
コード進行上で鳴らし続けることが大事です。
フレーズを弾くのではなく、
音を鳴らす、という感覚です。
ジャズを始めたばかりのピアニストは、
どうしても、
フレーズの良し悪しにこだわります。
それは、
クラシックや譜面ものの影響で、
フレーズが良ければよいアドリブだ、
そういう間違った解釈があるからです。
ジャズは、フレーズの内容だけで
良い悪いとはなりませんので、
フレーズを完成させることを
まずは止めましょう。
自分の出す音に耳を傾けて、
どんな音がするか、
自分なりの言葉で解釈しましょう。
それができれば、
どのタイミングでどんな音を出したいかが
分かってきますので、
結果、アドリブとなりますよ。
アドリブ上達に必要な、
ジャズピアノのキモをこちらにまとめています。
宜しければご覧くださいね。
https://keiko-onuki.com/jazzpiano/

アドリブ初心者の為の
体系的に学べるレッスン
ジャズピアノ&アドリブコーチ
性格気質と自己表現の研究家
音大&ジャズ研未経験で、ピアノブランク13年、30歳でコードを知る。
約8年間ジャズピアノの実態が分からなかったが、ある時ヒラメキが起こり、何を何からやったら、誰でもジャズピアノが弾けるのかが分かり、1日6時間くらいピアノに夢中になる。
2016年より1児の母をしながらリアル&オンラインコーチングレッスンを開始し、ゼロベースの初心者でも、1年以内にリードシートのみで、アドリブ、セッションに参加できる体系的なメソッドを提供中。
更に、なぜ自分はアドリブが弾けるようになったのかが、心理学や脳科学の観点で説明が出来ることが分かり、楽器・アドリブの熟達法と内面性の関係について、レッスン、YouTube、ブロブ、メルマガで語っている。