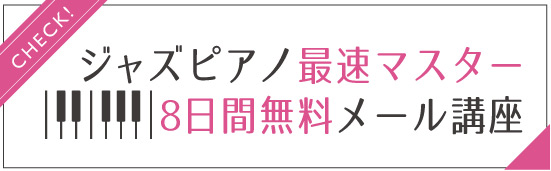ジャズピアノが格段に上達するために最初の2年でやること

もくじ
1年目は現場に出る
私のレッスンではある条件を満たした人を募集しています。
それは、セッション、レッスン、独学のいずれかを、自分なりにやった人です。
なぜなら、音楽は体験することから始まるからです。
特に、始めた2年目くらいまでの過ごし方で、上達のスピードが違ってきます。
具体的には、
1. ジャズピアノを始めた、最初の1年目は、未熟ながらもセッションに参加して現場を知る。
若しくは、自分なりに難しいことは抜きに、見よう見まねでやってみる。
2. 次の2年目から、本物のコードワークを理解して、スキルアップに集中する。
つまり、
1. 感覚、体感で演奏する。
2. 論理、知識を整理しながら演奏する。
というわけです。
完成のイメージを知っておく
なぜ、この順番なのか。
普通の人は、いろいろなことを知ってから、セッションのお店に行ってみよう~となりますよね。
ですが、この順番が逆転した時点で、ジャズピアノ上達への道からは、かなり遠ざかります!
それは、ジャズという現場がどんなものなのかを、先に体感して知っておくことが、大事だからです。
子供のように、理屈は抜きでいいから、先ずはやってみるのです。
すると、自分はあんな風に演奏したい、こういうところが難しいなぁ、といったことを現場、現実で知っているので、ゴール設定が明確になり、そこへ向かって自然と練習したくなります。
要するに、自分がどうなりたいのかのゴールが見えるから、やるべきことが分かり、練習したくなるというわけです。
取組む順番が大事
もし、「2」のコードワークやスキルアップを先にやろうとすると、どうなるでしょうか。
それは、理解出来ない、難しい、と感じやすくなり、ジャズピアノに対して、苦手意識を持ちやすくなります。
ジャズという現場を知らないので、イメージが湧きにくく、その状態で、コードワークをやっても理解、スキルの吸収が遅い、という状態に陥りやすくなります。
そのため、私のレッスン対象者は、ジャズピアノを始めて2年以上、とさせて頂いているのです。
ですが、まだ怖くて、セッションに参加したことがない、という方が多数なので、一人の生徒さんのためにセッションの時間も作って、現場を体験するという時間も設定しています。
先ずは、ジャズピアノを始めた1年目の頃は、出来なくても、演奏に参加する勇気がなくても、セッション、という現場に足を運ぶことをオススメします。
毎回、見学をすれば、常連さんと顔見知りになり、ブルースくらいやりませんか?などと、声をかけてもらえることもあります!
最初は、緊張したり、自分が何も出来なくて肩身が狭い思いをするかもしれません。
しかし、最初は誰でも、ゼロスタートです。
ここは、思い切ってジャズを知る、というところから始めると、後々の練習がやり易くなりますよ。

アドリブ初心者の為の
体系的に学べるレッスン
ジャズピアノ&アドリブコーチ
性格気質と自己表現の研究家
音大&ジャズ研未経験で、ピアノブランク13年、30歳でコードを知る。
約8年間ジャズピアノの実態が分からなかったが、ある時ヒラメキが起こり、何を何からやったら、誰でもジャズピアノが弾けるのかが分かり、1日6時間くらいピアノに夢中になる。
2016年より1児の母をしながらリアル&オンラインコーチングレッスンを開始し、ゼロベースの初心者でも、1年以内にリードシートのみで、アドリブ、セッションに参加できる体系的なメソッドを提供中。
更に、なぜ自分はアドリブが弾けるようになったのかが、心理学や脳科学の観点で説明が出来ることが分かり、楽器・アドリブの熟達法と内面性の関係について、レッスン、YouTube、ブロブ、メルマガで語っている。