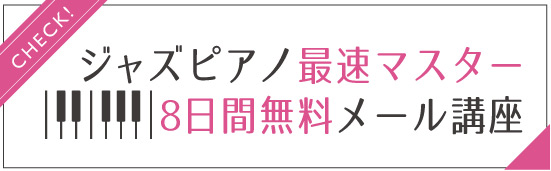コードはコードの通りに弾かなくても大丈夫です

もくじ
コードはあくまで共通認識
急に暖かくなって、つい、うとうと眠くなってしまうような気候になってきました。
とは言いながららも、年度末で何かと忙しかったり、変化の時期ですので落ち着かないかもしれませんね。
私は次年度は、子供の学校の役員になっているので、既に引き継ぎをやっています。
さて、今日のテーマはコードはコードの通りに弾かなくても大丈夫だよ、というお話です。
ピアニストの役割として、他の楽器よりもコードを出すことが求められるため、コードを意識して弾くことが多いですよね。
アドリブ慣れしない頃、理論がいまいち良く分かっていなかった頃の私は、書いてあるコードの通りに弾かなきゃダメだと思い込んでいました。
しかし、、、リードシートに書いてあるコードは、あくまで共通認識として書いてある、という程度に思っ大丈夫だよ!というのが今日お伝えしたいことです。
アドリブ初心者が知っておいた方がいいコードの捉え方
9分15秒
他のコードでも大丈夫な例
上記動画でもお話していますが、こちらでももう少し詳しく説明しますね。
例えば、酒とバラの日々という曲は、ジャズセッションでもよく選曲されるものです。
この曲を取り上げて、他のコードでも大丈夫だよというのを説明しますね。
キーはFで、冒頭の4小節に、よく使われるコード進行がこちらです。
F△7 ⇒ E♭7 ⇒ Am7♭5 ⇒ D7
例えば、私であれば2小節目のE♭7を、Gm7に変えてもいいよという案を思いつくんですね。
どうして、Gm7に変えてもいいの??と思う方のために、少し説明しますと・・・
キーFで出来ている曲なので、Fのダイアトニックコードであれば、何を使っても間違いでは無いというのが、一つの考え方です。
ダイアトニックコードが分からなければ、以前こちらで説明していますよ。
https://keiko-onuki.com/2021/08/13/21-8-13/
あとは、メロディの音が、コードトーンに含まれている場合も、そのコードを使う案としては、比較的候補になりやすいです。
ここで言えば、2小節目冒頭のメロディがGになっているので、Gm7を持ってきています。
更に上級者であれば、もっと掘り下げて、そのコードが持つスケールの中にメロディの音があれば、そのコードを使う候補にもなります。
実はこれにあたるのが、E♭7なのです!
E♭7は、リディアン7というスケールが使えますので、メロディの内容を見ると、リディアン7に含まれる音が、バッチリメロディの音になっています。
特に、Aという音がE♭7から見ると、#11なので、これはリディアン7の特性音であり、最もリディアン7らしく聞こえるので、これを強調したかったからE♭7をつけていると見ることが出来ます。
どのコードでもOKを前提にしよう
実は、どのコードでもいいんだ、たまたまこのリードシートはこのコードなんだ、という感覚が、コード音楽やアドリブをする上では大事な感性になります。
このコードじゃなきゃダメという考えが薄くなった方が、リラックスして演奏することも出来ますし、実は私が過去にチラと話した暗譜する力、譜面を見ないで弾ける力にも繋がってきます。
知識は多少必要ですが、この時点で話が??となっている方は、一先ず、コードパターンは何通りも存在すると思うといいですよ。
ジャズピアノで最初に知っておいた方がいい内容はこちらにまとめています!
https://keiko-onuki.com/jazzpiano/

アドリブ初心者の為の
体系的に学べるレッスン
ジャズピアノ&アドリブコーチ
性格気質と自己表現の研究家
音大&ジャズ研未経験で、ピアノブランク13年、30歳でコードを知る。
約8年間ジャズピアノの実態が分からなかったが、ある時ヒラメキが起こり、何を何からやったら、誰でもジャズピアノが弾けるのかが分かり、1日6時間くらいピアノに夢中になる。
2016年より1児の母をしながらリアル&オンラインコーチングレッスンを開始し、ゼロベースの初心者でも、1年以内にリードシートのみで、アドリブ、セッションに参加できる体系的なメソッドを提供中。
更に、なぜ自分はアドリブが弾けるようになったのかが、心理学や脳科学の観点で説明が出来ることが分かり、楽器・アドリブの熟達法と内面性の関係について、レッスン、YouTube、ブロブ、メルマガで語っている。